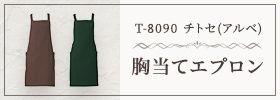これだけは押さえて!飲食店開業に最低限必要な資格と手続きまとめ
飲食店を開業すると決めたらメニューを考えたり、お店の内装に想像を膨らませたり、準備は大変ながらもワクワクしますよね。
でもちょっと待って!開業に必要な資格や手続き等の申請は進んでいますか?
きちんとした手順を踏まないと、お店のオープンに間に合わない事態や最悪罰則を受けるケースも…。
今回は飲食店を開業するために、最低限必要な資格2つと届け出・手続き9つを紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
INDEX
必要な資格

飲食店開業に必要な資格はそれほど多くありません。
中には資格が免除されたり、必要がなかったりする場合もありますので、まずは調べてから資格取得を始めましょう。
食品衛生責任者は、飲食店を開業する上で必ず取得しなければならない資格です。
各都道府県の食品衛生協会が主催する講習会を受講することで取得できます。
受講するには事前予約が必要となり、費用は1万円程度、講習期間は1日のみです。
防火管理者は、収容人数が30人以上の飲食店を開業する場合に必要となる資格です。
ここでいう「30人」には客席数だけでなく、従業員数も含まれますので注意しなければなりません。
各地の消防本部などが主催する講習会を受講しますが、受講区分が2つに分かれています。
店舗の延べ面積が300㎡以上の場合は「甲種」、300㎡未満であれば「乙種」です。
講習の受講日数がそれぞれ異なりますので、自分の店舗にあった種別を選びましょう。
意外!?調理師免許は必要ない
飲食店開業にあたって、調理師の免許が必要だと思っていませんか?実は調理師免許がなくても、飲食店を開業することは可能なのです。
調理師免許を持っていると、上記で述べた「食品衛生責任者」の講習が免除されます。
メリットはありますが、必須ではないということを覚えておくと良いかもしれません。
必要な届け出・手続き
届け出や手続きは資格に比べて数も多く、ちょっと面倒に感じてしまうかもしれません。
一つずつ確実に申請していきましょう。
飲食店開業で真っ先に思い浮かぶ保健所への申請で、どのような形態の店舗でも必要になります。
まずは事前相談を行い、店舗が完成する10日程前までに申請します。
申請には食品衛生責任者の資格証明が必要ですので、この時までには資格を取得しておきましょう。
店舗が完成したら保健所から調査員が派遣され、施設や設備のチェックをします。
チェックの際には申請者も立ち会い、問題がなければ許可が得られます。
防火管理者が必要な店舗を開業する際に、消防署へ届け出ます。
先述の資格を有した者が、確実に在籍していると証明するものです。
店舗の開業前までに届け出る必要があります。
収容人数30人以下の店舗開業であれば、手続きは不要ということになります。
建物や建物の一部を新たに利用する場合に、消防署へ届け出ます。
使用を始める7日前までに、必要事項を記入した書類を用意し提出しなければなりません。
新築の建物に店舗を開業する場合だけでなく、既存の建物にテナントとして入居し開業する場合にもこの届けは必要となります。
こちらも消防署へ届け出るものになりますが、おそらくほとんどの飲食店で必要となるでしょう。
火を使用する設備等には、「厨房設備」「炉」「温風暖房機」「ボイラー」が含まれています。
これらを全く使用せずに飲食店を開業することは難しいですよね。
設備の設置する前に消防署へ申請し、設置後に検査が実施されます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、所轄の警察署に提出します。
午前0時から午前6時までの間に、お酒をメインで提供する飲食店を開業する場合には届け出が必要になります。
警察署への申請期限は開業の10日前までです。
午前0時までに営業終了する店舗であれば、そもそもこの届け出は必要ありません。
その他に午前0時以降に営業し、お酒を提供していても届け出が不要といったケースもあります。
例えば、食事がメインで訪れる人が多いファミリーレストランがその一つです。
開業予定の店舗にこの届けが必要かどうか、自身で判断がつかない場合には一度相談に行かれることをおすすめします。
独立して飲食店を開業することになった場合、個人事業として始める人が多いのではないでしょうか。
その際には個人事業の開業・廃業等届出書、いわゆる「開業届」を所轄の税務署に提出します。
提出期限は原則として開業した日から1ヶ月以内となっています。
この先、個人事業主として所得を得て、税金を納めていくにあたり必要な手続きです。
忘れずにきちんと行うようにしましょう。
自分ひとりだけで開業するのではなく、従業員を雇っての飲食店開業を考えている人もいるかもしれません。
従業員を雇う場合にまず必要になってくるのは、労災保険の加入手続きです。
労災保険はアルバイトやパートといった非正規雇用はもちろん、たとえ短期のアルバイトであっても強制加入となっています。
従業員の雇用を開始した日から原則10日以内に、労働基準監督署で加入手続きを行う必要があります。
雇用保険の加入手続きは公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
1週間の所定労働時間が20時間未満など一部除外要件もありますが、適用除外とされる従業員以外は全員加入対象です。
適用となる従業員を雇った場合には、加入手続きが雇用者の義務となります。
加入手続きの期限は、原則、雇用を開始した日の翌月10日までです。
ここでいう社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
社会保険は個人事業であれば加入は任意ですが、法人を設立した場合は強制加入です。
どういった形態で飲食店を開業するかによって、手続きをするべきか否かは変わってきますので、比較検討しながら開業の準備を進めていきましょう。
もし、手続きが必要であれば速やかに日本年金機構へ書類を提出します。
まとめ
いかがだったでしょうか。
資格や手続き等には期限があるものや、時間がかかるものもあります。
お店のオープン日から逆算して、日程を調整するのがおすすめです。
くれぐれも時間には余裕を持って、準備を進めるようにしましょう!